現在、米国を中心に景気が回復し、そろそろ段階的な利上げ方向に舵取りをしたい中央銀行が増えてくるなか、株や債券・不動産等、市況に左右される投資家というのは何を考えておくべきかを整理したいと思います。
リーマンショック後の金融政策と財政政策の両面が功を奏し、大きな回復を果たしたようにも見えますが、その副作用を常に理解しておくべきです。
ここではまずリーマンショック後に米国を中心に行なった政策、その政策がどのように影響したか、そして現在の景気をどう考えるべきかをまとめていきたいと思います。
リーマンショック後に行なった各国の経済政策
リーマンショックとは米国のリーマン・ブラザーズ証券が、不動産を証券化した商品のサブプライムローン問題から証券化商品の値下がりにより、破綻に追い込まれたことが景気に大きく影響し、世界経済が崩壊したことを指してします。
その時に行なった経済政策としては大きく「金融政策」、「財政政策」の2点が挙げられます。
政策金利の引き下げ
政策金利の引き下げは基本的な景気の調整で各国が行なっている伝統的な金融政策です。
各国中央銀行が政策金利という金利のベースとなるものを設定しており、この上下によって景気の調整を図るものです。
この時アメリカも実質ゼロ金利付近まで政策金利を引き下げ、日本やEUに関しては、なんとマイナスという非伝統的な水準まで引き下げたことでこの効果がきちんと波及するのか話題となったこともありました。
国債の買い入れ
国債の買い入れは各国中央銀行が市場に出回っている国債を買取する政策です。景気がリーマンショックのように急激に落ち込んだ場合に起きる現象というのは、銀行の貸し渋りです。どこまで景気が落ち込むかわからないことから、融資に対して審査を厳格化させ企業に対しての融資に消極的な状況になります。
このような動きが市場全体で浸透し始めると、市場のお金の流動性は悪くなるため、景気は悪化の一途を辿るようになっていきます。そのため、その動きを止めるために、中央銀行が政策で対応するようになります。
金利の引き下げも融資を受けやすいようにするための金融政策ですが、中央銀行が国債を買い入れするという動きは、市場の流動性を供給するという役割を果たします。
この国債の買い入れというのは、今まで行なったことのなかった「非伝統的金融政策」と言われており、具体的に見込まれた効果は2つあります。
① 国債の強力な買い手の出現により、長期金利が低下し長期的な低金利状態が予想されるようになる。(長期の期待インフレ率が低い状態となる。)
② 中央銀行が民間銀行から国債の買い入れを行うことによって、国債購入代金分が民間銀行に供給されるようになるため、大量の資金が民間銀行を通じて市場に供給されるようになる。(※民間銀行が資金に余裕が出来る事で貸し出しを行ないやすい環境になり、資金の流動性を確保することが狙いである。)
この2つが「非伝統的金融緩和」の見込まれた効果だったのですが、②の買い入れにより生じた資金というのが違った方向にも向かい始めることになります。
国債買い入れにより生じた資金はどこへ?

中央銀行が、市中の民間銀行から国債を買い入れることによって市場に資金を供給し、資金の流動性を確保したかった事は理解できたかと思いますが、果たして実際に中央銀行の思惑通りに動いたのかというと、そうではない動きも見られました。
民間銀行はあくまで株式会社であり、政策金利がゼロ金利付近になると、貸出金利も連動して低下してしまうことから、融資による利息からの収益も低下してしまいます。
また銀行の貸し出しというのは、資金に余裕があるからといってジャブジャブ貸出金額を増加させるわけではありません。
そのため、国債を中央銀行に売却した資金を運用して効率的に収益をあげるには何がいいのか?と考えた時に向かったのが、「国債」と「株」になりました。
国債に関しては、毎月中央銀行が巨額の国債を買い入れすることから大きな買い手がいるため、価格が低下する可能性というのは著しく低い状態でした。
また株は「緩和マネー」と呼ばれるもので、余った資金を株に流すことで株高の恩恵を受けることが出来るようになり、この有価証券投資に資金を費やす銀行が大きく増加しました。
つまりこれが意味することは「中央銀行が資金の流動性を確保するために国債を買い入れするも、実体経済以上に余ってしまった資金が株に流れたことで株高が進んでしまっている」ということです。
ちなみに日本はどうなのか?
ここで少し日本にも目を向けて見ましょう。
日本銀行が行なった政策というのは、米国と同様に政策金利を引き下げました。それも日本の場合はマイナス金利という「非伝統的金融政策」を導入し話題になりました。
預金をすると預けた方が利息を取られるという今まで聞いたことのない状態を示しています。
また米国が行なった「国債の買い入れ」も同様に行い、同じような結果となりました。
日本銀行が別途、追加で行なったことは「ETFの買い入れ」です。ETFとは上場投資信託を指していますが、このように中央銀行が直接的に市場に介入するというのは珍しい手法でした。
金額は2018年で年間6兆円ほど買い入れしており、これが数年間続いていることから、数十兆円規模で日銀が市場に介入していることになります。
これによって実体経済以上に日経平均株価が押し上げられていると言われており、一部では4,000円以上は押し上げられているのではとも言われています。
ではなぜこのリーマンショック後の政策が、今後の不動産を含めた市況に影響があり、理解しておくべきなのかを次に解説します。
今後投資をする上で注意すべきこと

これまで説明してきたことで、現在の株価の水準と実体経済の状況というのは相違があるのではないかということが理解できたかと思います。
私はこれを伝えたいため記載しました。現在の株価というのはある意味「経済にモルヒネを打った状態が継続し、実体以上に数字が良く見えている部分もある」ということです。
また景気は繰り返すと言われますが、2008年のリーマンショックから10年以上が経過しました。
米国では出口戦略として利上げが行なわれ始めましたが、景気が大分良くなってきたにも関わらず、トランプ大統領の減税政策によって企業利益の先取りを行なってしまったことから、米国の株価が一段高となってしまい、足元ピークの兆候を予感するような数字が徐々に出始めています。
日本でも、世界の景気頭打ちの雰囲気が影響し始め、株価も下落する展開で今年はスタートしています。
居住用不動産の成約件数等も頭打ちが鮮明になり、ここ数年間海外の投資家が緩和マネー等で日本の不動産に継続的に入ってきていた反動が大きく出始めた状況です。
供給過多の状態の中で需給バランスを考えると、この動きに違和感はなく、むしろ自然の摂理の中の素直な動きとも言えるでしょう。
つまり今後投資をする上で考えるべきは「モルヒネを打ち続けた結果、効果がなくなってきており、政策対応もできない環境下、景気後退の足音が聞こえ始めている」という段階なことを覚えておくべきでしょう。
また、リーマンショック時と現在の状況とでは大きな違いがあります。それはリーマンショック後は政策金利に引き下げ余地があったことや、国債買い入れによって市場に資金が供給出来ていましたが、現在は両者ともに行なってしまっていることから対策が限定的にしか打てないということです。
もちろん放置することは有り得ませんが、政策対応というものは限界があるため次に来るときのクラッシュは、緩和を行なった資金も含めてクラッシュしてしまうため、予想以上の影響が出ることは危惧すべきでしょう。
投資対象は選別して、資金も一括で投資するのではなく、時間をズラして、できる限りリスクを低下させるようにする等工夫が必要な時期に入ってきています。
次の10年はこれまでの一方的な株の上昇は見込みにくいため、情報をきちんと仕入れながら自分自身で判断できるような金融リテラシーが必須の時代と言えそうです。
増税時代を生き抜きための『スマート税金セミナー』
↓ 詳しく知りたい方は画像をクリック ↓
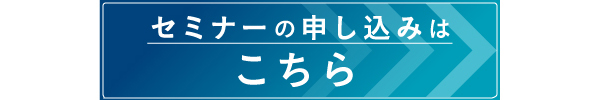
【記事筆者】

-
学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行に入行し、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。
【保有資格】証券アナリスト
最新の投稿
 マーケット情報2019.08.20ECB(欧州中央銀行)の金融政策の歴史と今後の行方について
マーケット情報2019.08.20ECB(欧州中央銀行)の金融政策の歴史と今後の行方について マーケット情報2019.07.29消費税増税後の外国為替の値動きとは?円高?円安?
マーケット情報2019.07.29消費税増税後の外国為替の値動きとは?円高?円安? マーケット情報2019.06.30不景気の株高とは?その対応法を解説
マーケット情報2019.06.30不景気の株高とは?その対応法を解説 資産運用2019.06.12【仮想通貨】ビットコイン上昇の理由は?5つのポイントを解説!
資産運用2019.06.12【仮想通貨】ビットコイン上昇の理由は?5つのポイントを解説!

